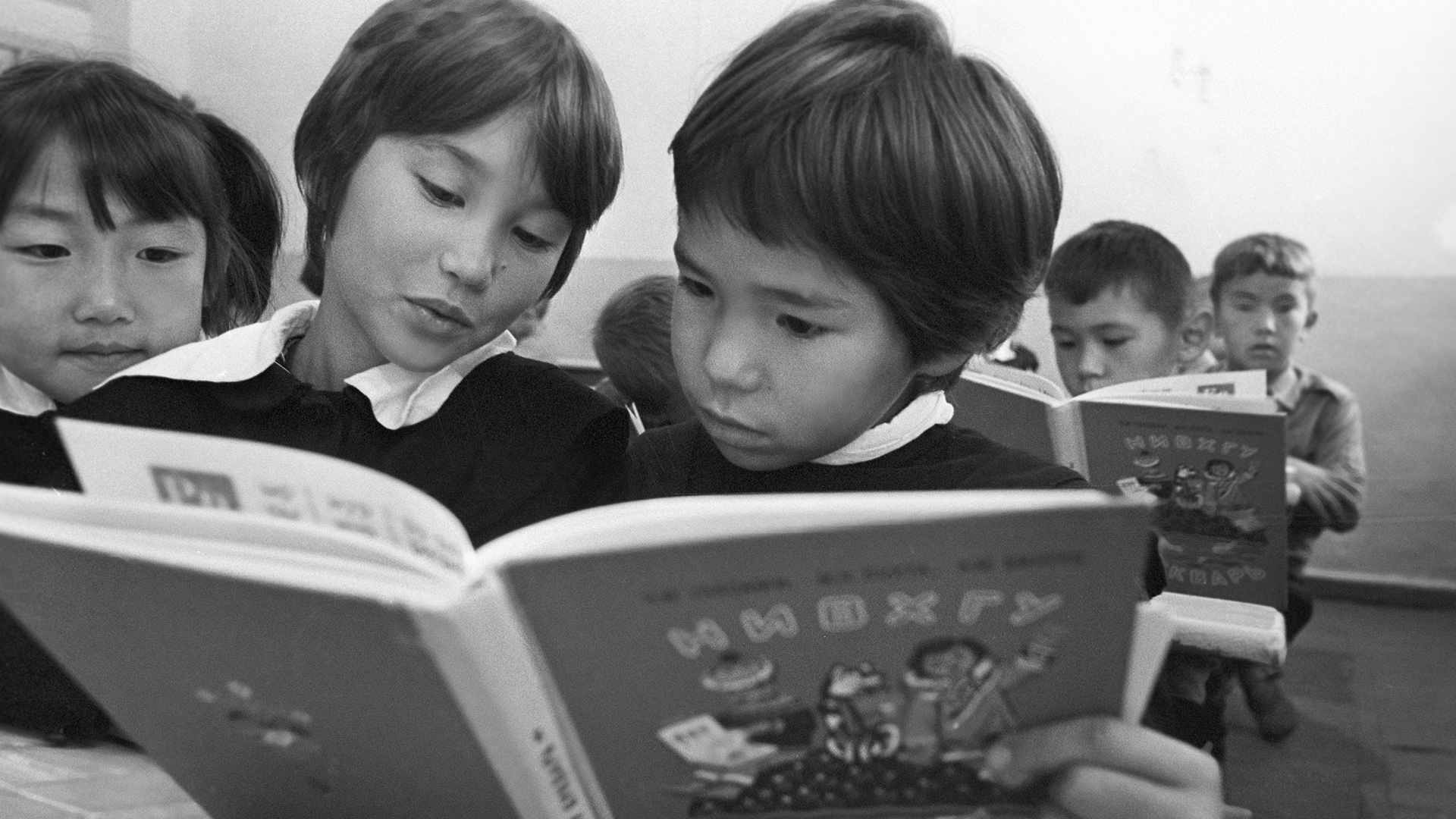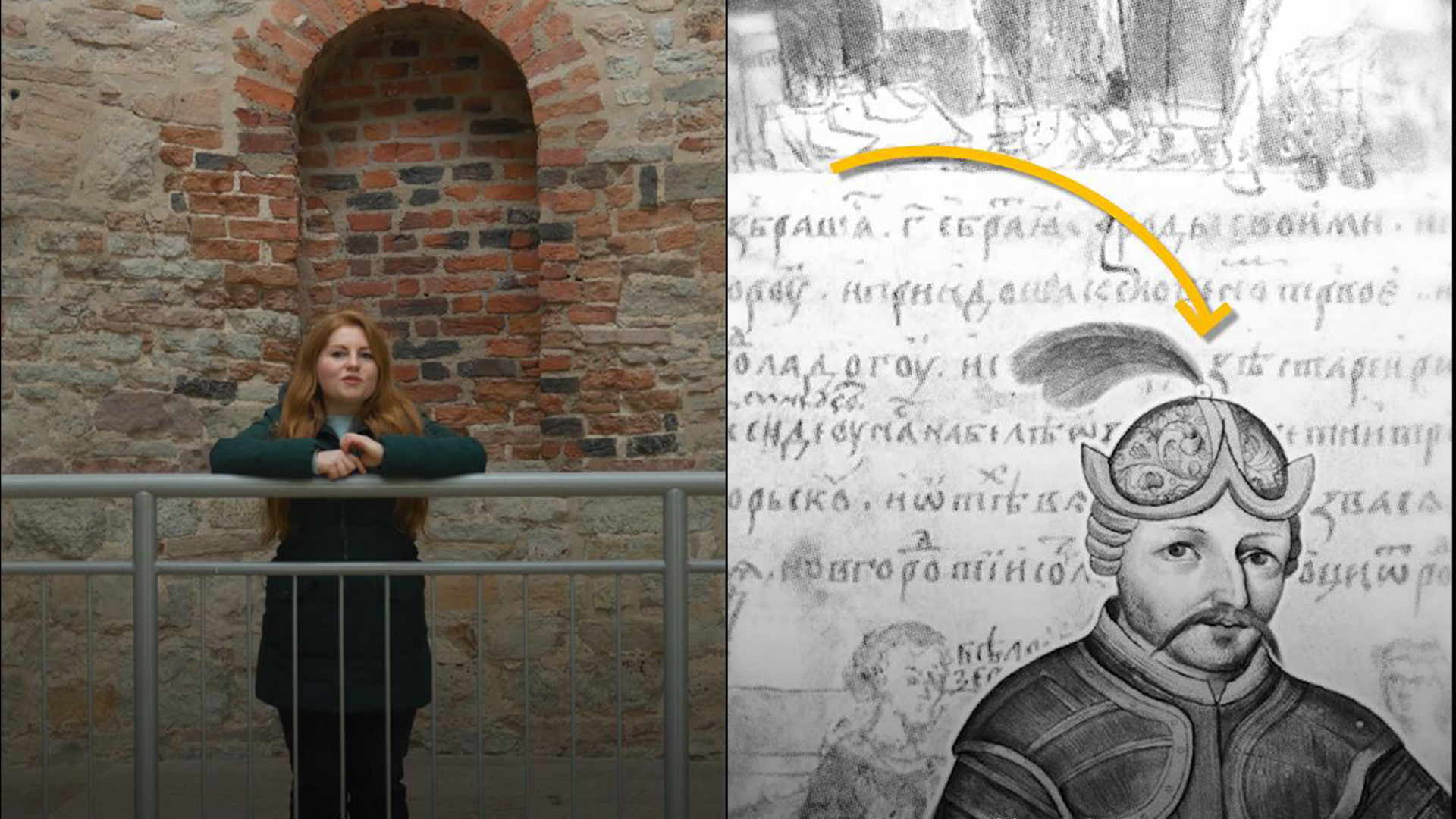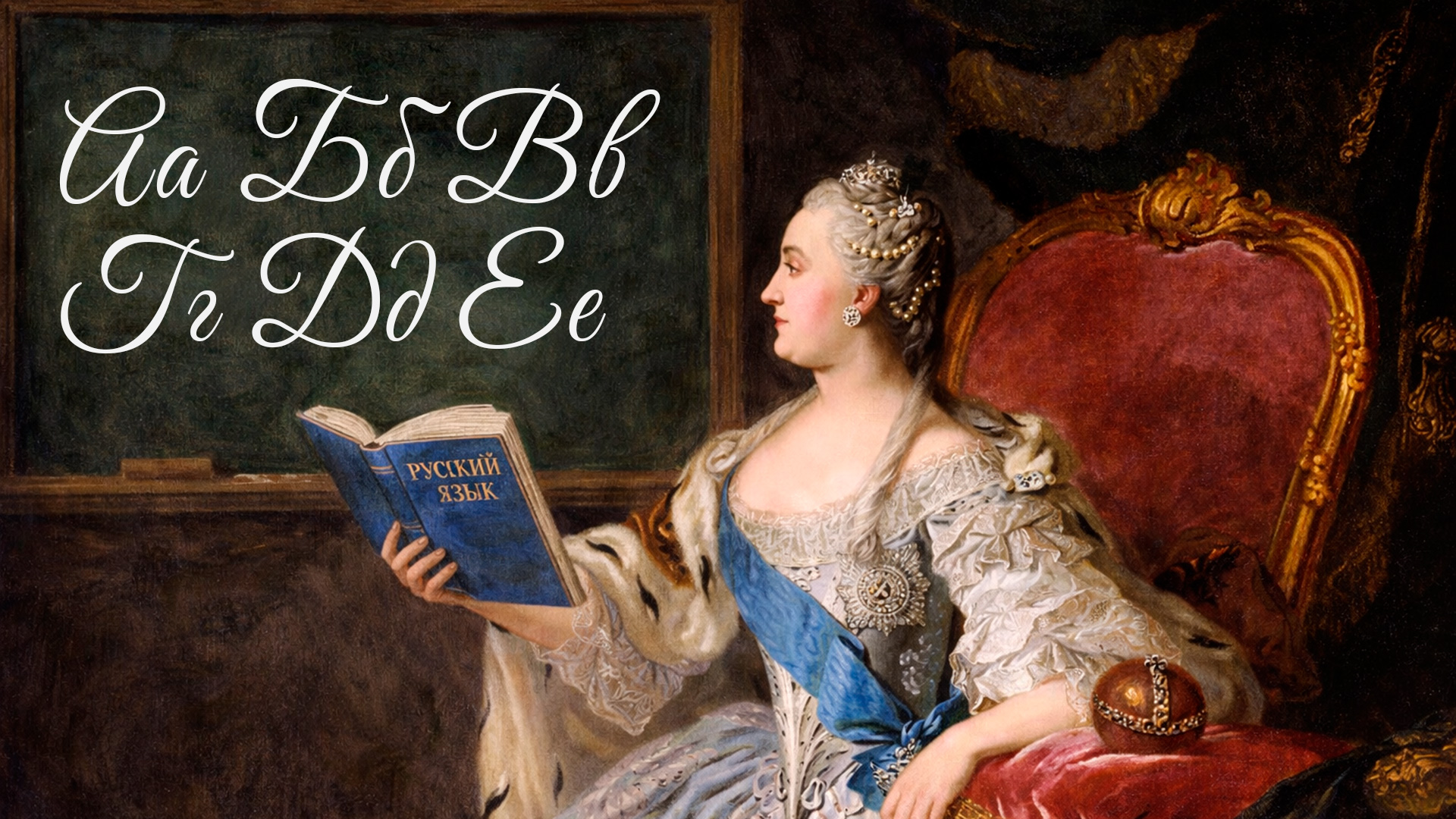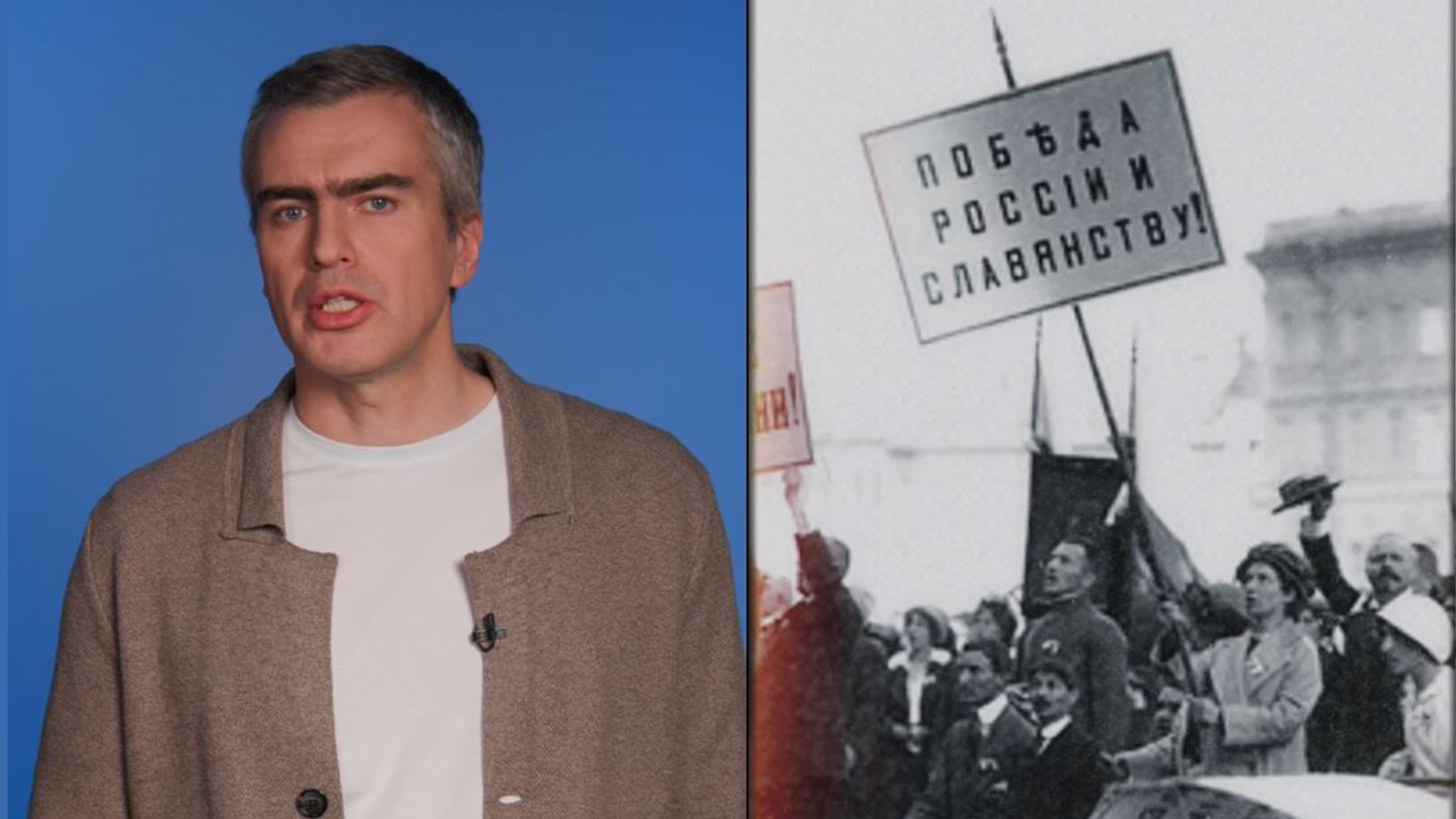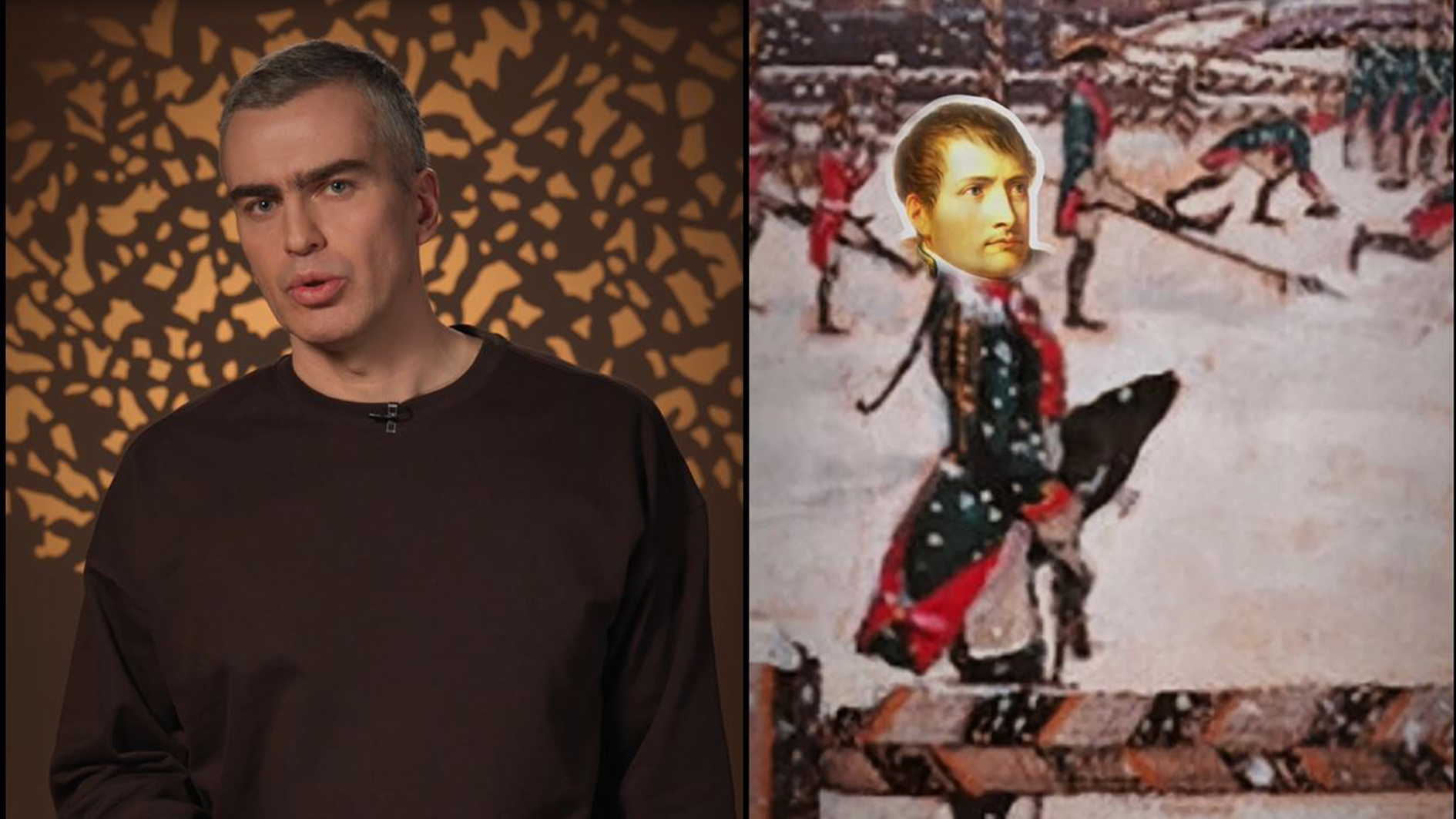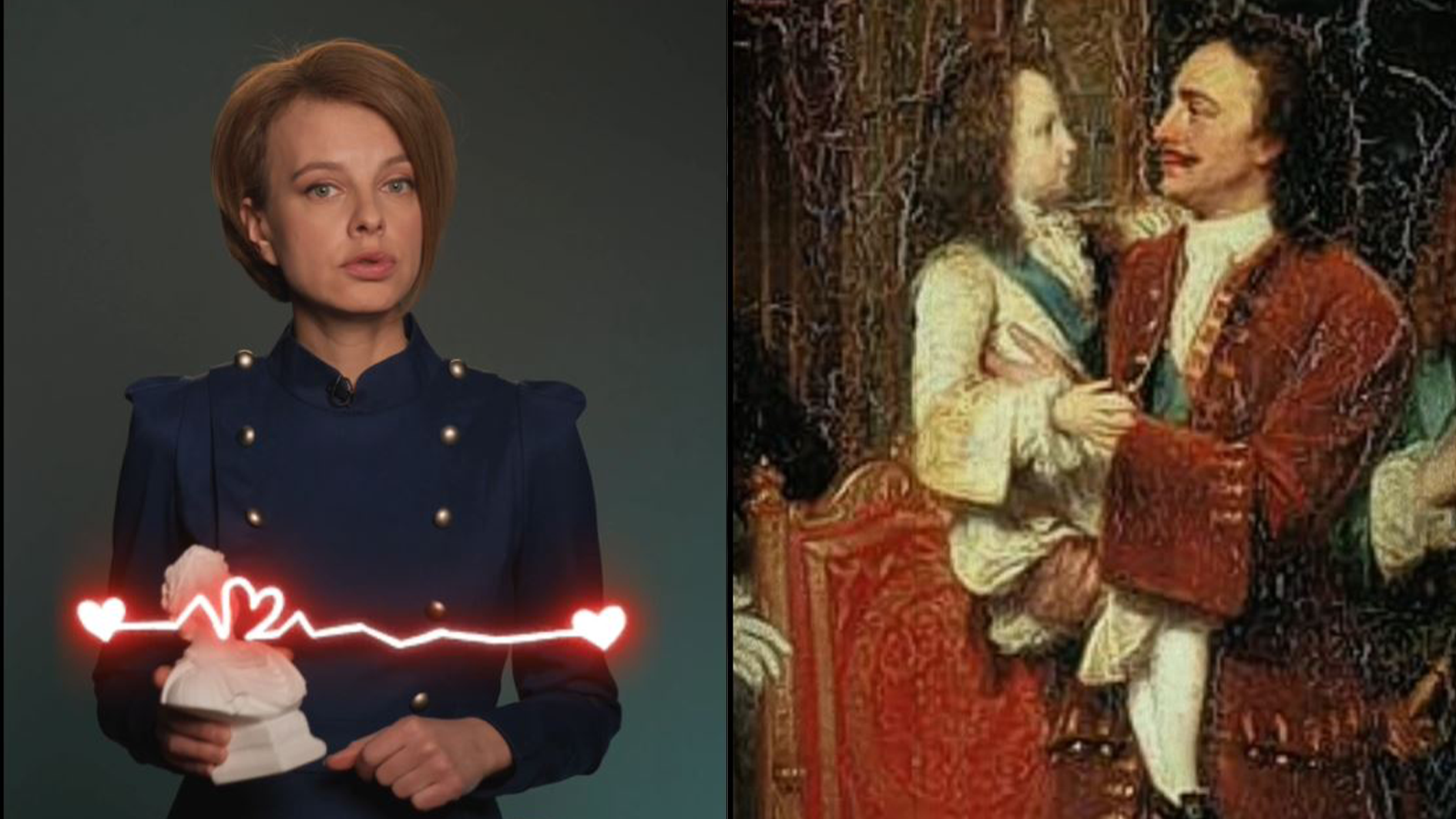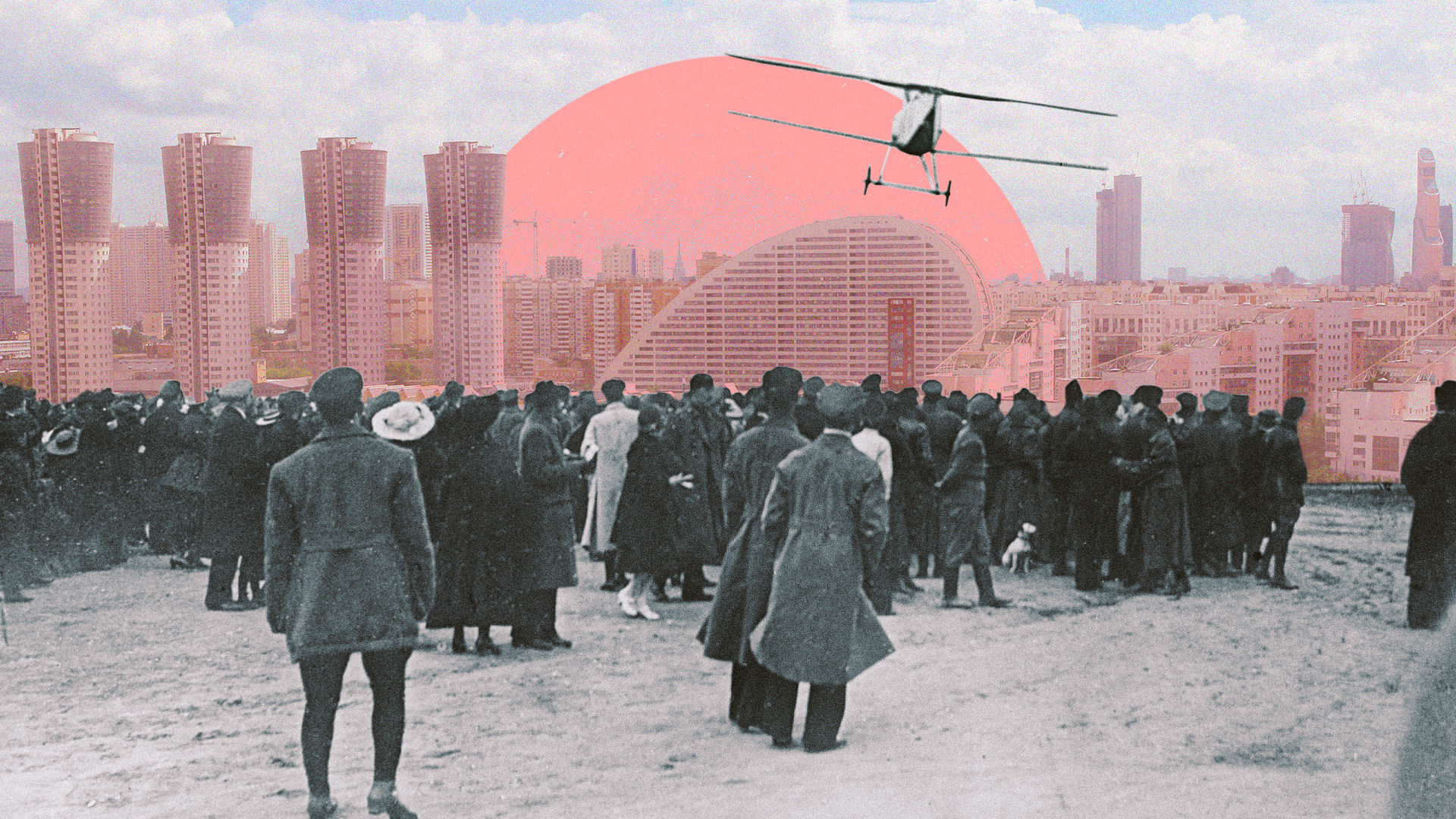
ツァーリの鐘、鋳造から290年

世界最大の鐘に秘められた試練の歴史。
1733年、モスクワ・クレムリンのイヴァノフスカヤ広場には巨大な坑道が掘られ、4基の鋳造炉が建設された。作業にあたったのは約200人。アンナ・ヨアーノヴナ皇后の勅命により、世界最大の鐘を鋳造するという前例のない計画が進められていた。

しかし、この壮大な試みは困難の連続だった。翌年、2基の炉が故障し、溶けた金属が地面へ流出。続いて火災が発生し、木造の構造物はすべて焼失した。
それでも職人たちは作業を続け、1735年11月25日、ついに鐘は鋳造された。坑道で磨き上げられ、キリスト、聖母マリア、諸聖人、そして皇帝アレクセイ・ミハイロヴィチとアンナ皇后の姿が施された、壮麗な装飾が特徴であった。
だが1737年、再び災厄が訪れる。火災がクレムリンを襲い、燃え落ちた木造建築物が鐘の上に崩れ落ちた。職人たちは消火のため鐘に冷水を浴びせかけたが、その急激な温度変化により亀裂が生じたとされる。伝承によれば、この時に外れ落ちた巨大な破片が、坑道に残されたままだったという。
完成した鐘「聖母被昇天の鐘」は、重さ202トン、高さ6.24メートル、直径6.6メートル。現存する鐘として世界最大の規模を誇る。
1836年、長らく地中にあった鐘はついに引き上げられ、台座の上に設置された。頂部には王権を象徴する銅製の宝珠と金メッキの十字架が掲げられ、その威容から「ツァーリの鐘」(「ツァーリ・コロコル」)の名で呼ばれるようになった。