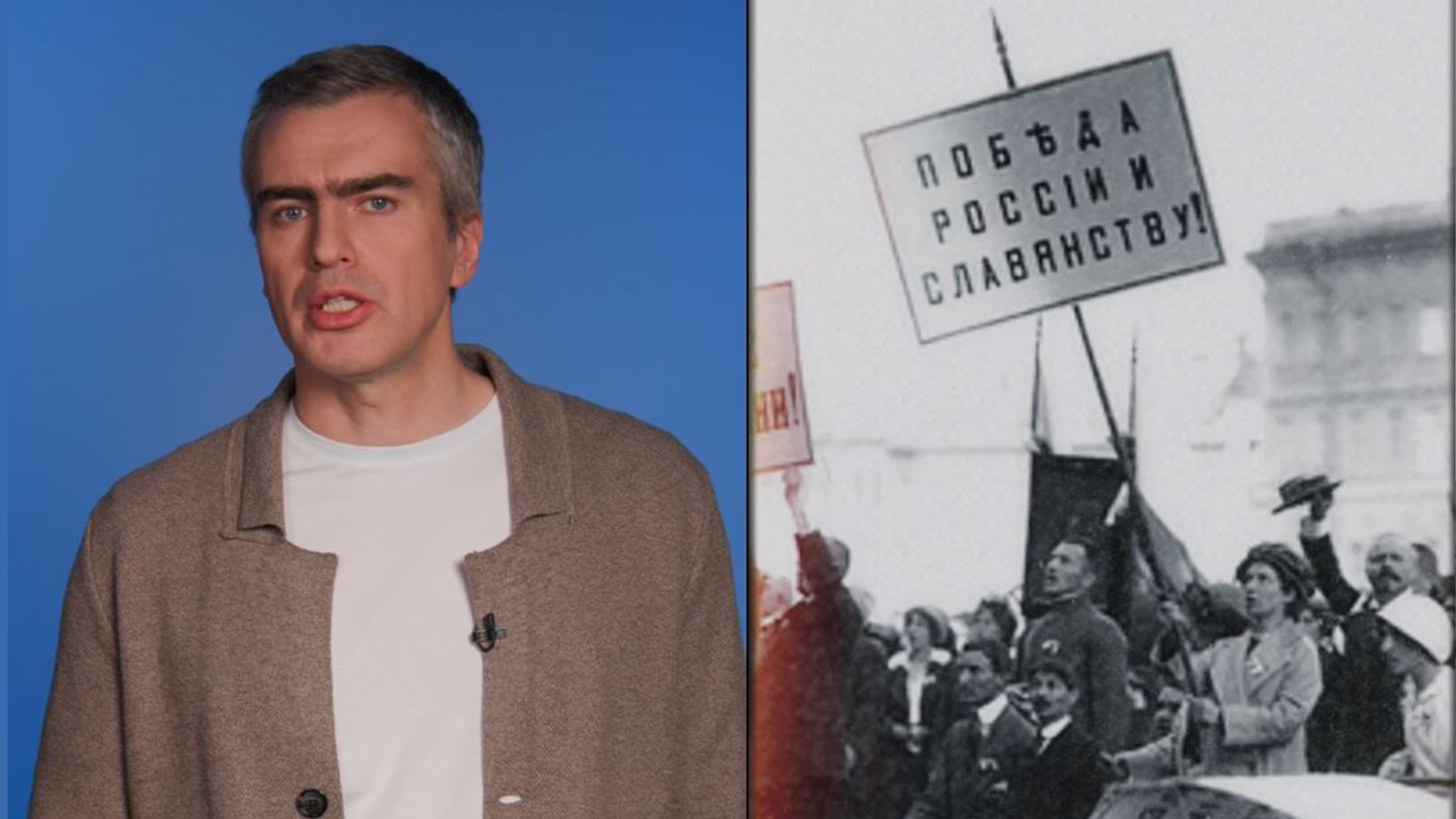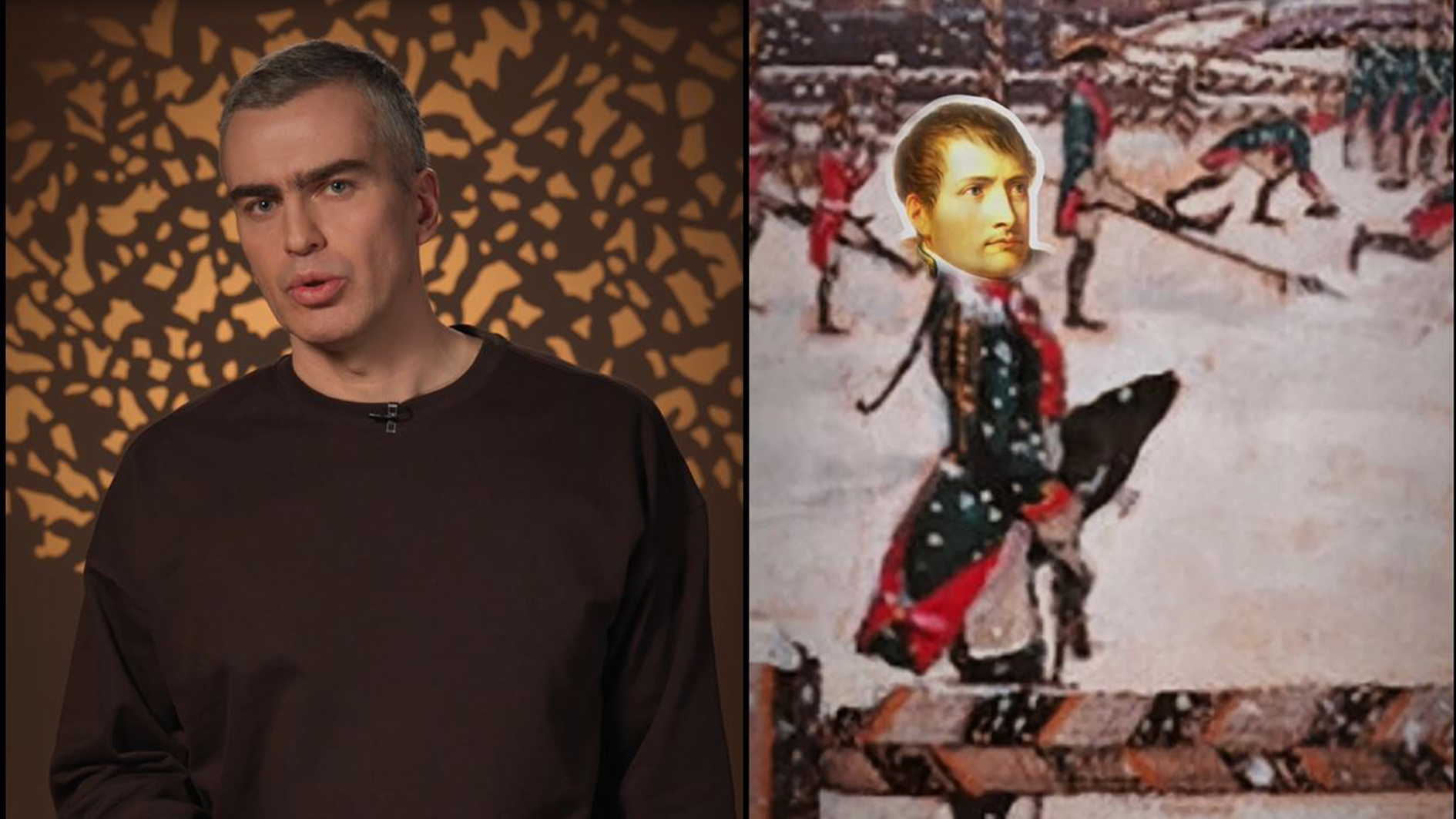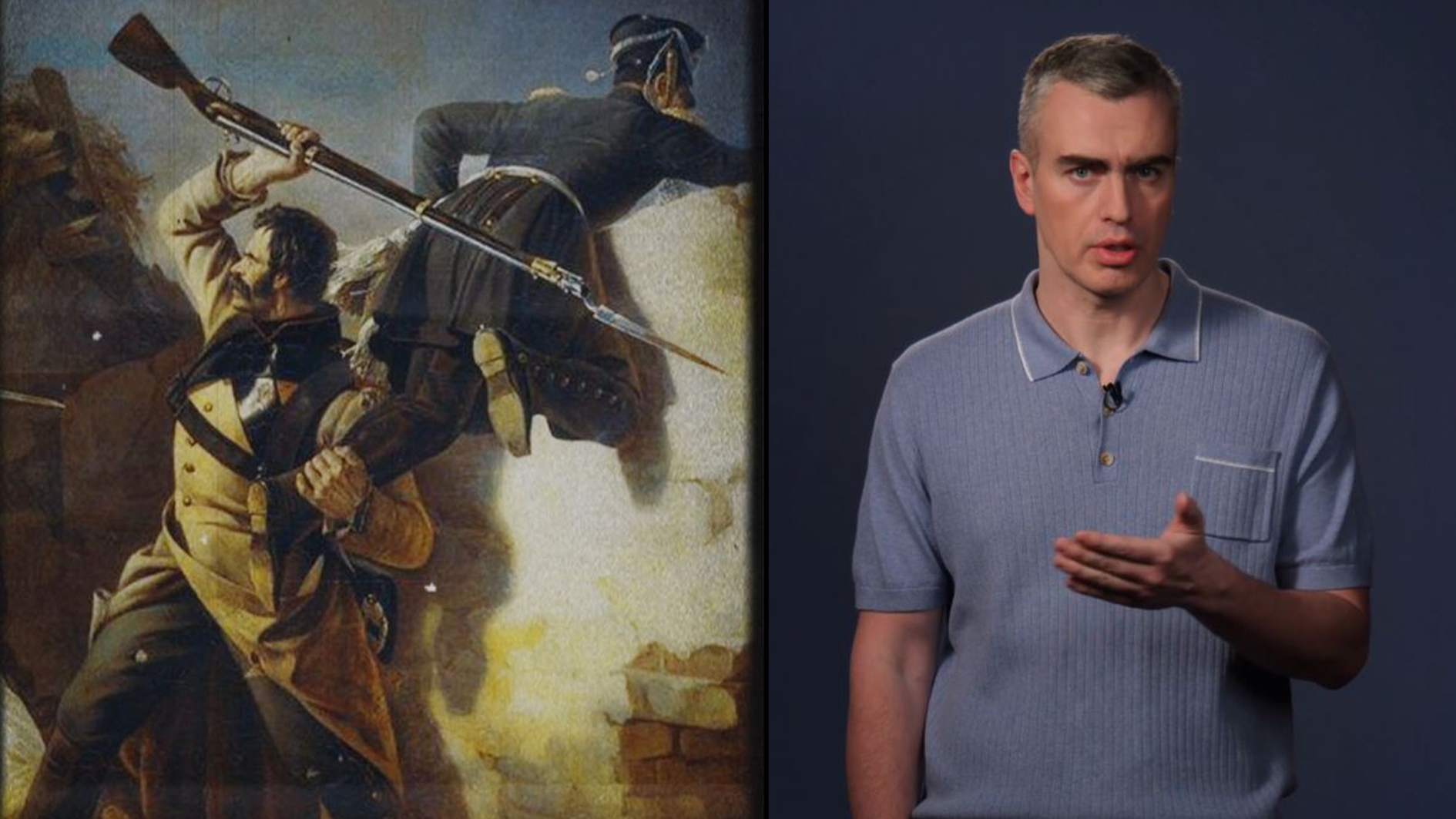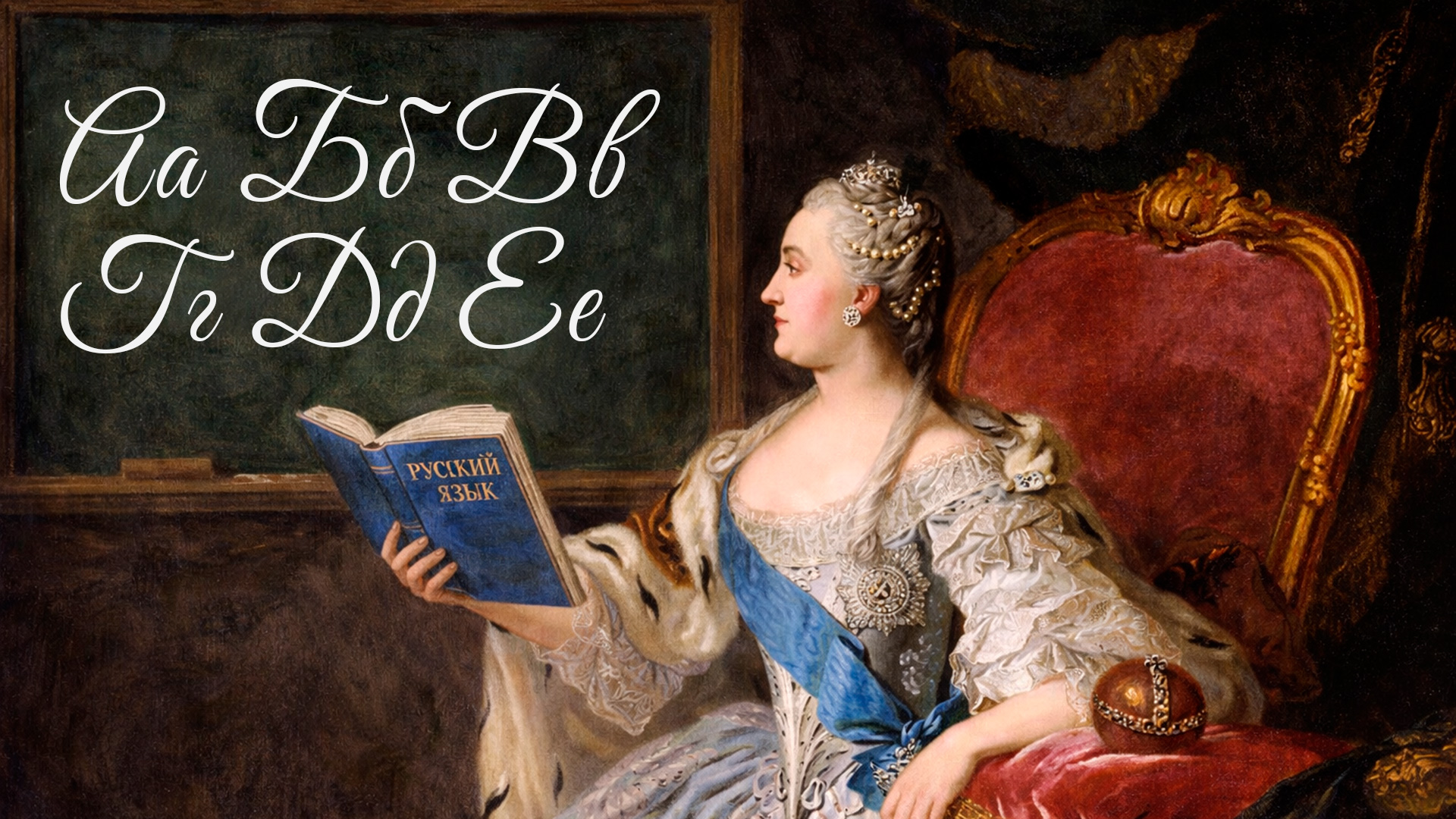
いかにしてロシアの科学者イワン・ミチューリンは自然法を変えたか

我々に、自然の恵みを待つ余裕はない。その恵みを取ることが我々の課題である」。ロシア人なら誰でも知っているフレーズだが、その出典を知る人は少ない。これはメタファーではなく、文字通りの意味だ。この言葉の主は、ロシア・ソ連の著名な品種改良家イワン・ミチューリン(1855 - 1935)である。彼は植物の生態そのものを変えてきた。
ミチューリンは5歳の時から父親の男手一つで育てられた。父親はその父祖たちと同様、園芸に熱中し、息子にも自然と園芸への興味を植え付けた。幼いミチューリンは科学に関心を示し、8歳の頃には様々な接ぎ木の方法を会得し、父親の養蜂と花園を手伝い、空き時間はひたすら生物学に関する読書に明け暮れた。
地方の学校を修了後は首都のリツェイ(高等学習院)に進学する計画だったが、一家の窮乏と借金返済のための領地売却のため、頓挫した。ミチューリンはリャザン市のギムナジウムに進んだが、ほどなくして学校幹部に対する不敬を理由に退学処分となった。その後は鉄道駅の事務員として働き、早々に駅長補佐になって、電信や電気を学んだ。

1875年、薄給にも関わらずミチューリンは屋敷を借りて、品種改良のための最初の育苗所を作った。鉄道で勤務を続けるかたわら彼は種子や苗、専門書の購入に給料を注ぎ込み、妻も彼を全面的にバックアップした。
根気よく続けた研究は、やがて実を結ぶ。彼は耐寒性の高いリンゴ、洋ナシ、プラムの品種を開発し、初めてロシア中部でセイヨウミザクラやアーモンド、ブドウなどの栽培に成功するといった、目覚ましい成果を上げた。ロシアで栽培される果物は、一気に多様化したのである。ミチューリンは近代的な品種改良法の基礎を築き、その手法は現在も世界中で使われている。

ミチューリンの名声は、やがてロシア国外にまで響いた。外国からも仕事の依頼が来るようになり、1913年にはアメリカから公式に招聘されるが、これは固辞している。
革命後、彼の事業はレーニンからも高く評価され、ソ連政府の援助を得た。ミチューリンは国を代表する品種改良家として国家勲章を授与され、彼の育苗所をベースに科学研究所が設立された。ミチューリンは専門教育を受けていなかったものの、生物学博士、ソビエト科学アカデミー名誉会員に任じられた。

I.V.ミチューリン生誕170周年を記念して、ダーウィン博物館では特別展「園芸と園芸家たち」が開催中。画家ヴィクトル・エフスタフィエフの作品、19世紀の珍しい園芸書、ミチューリンの生涯と研究を物語る遺品の数々などを展示。特別展は12月14日まで。