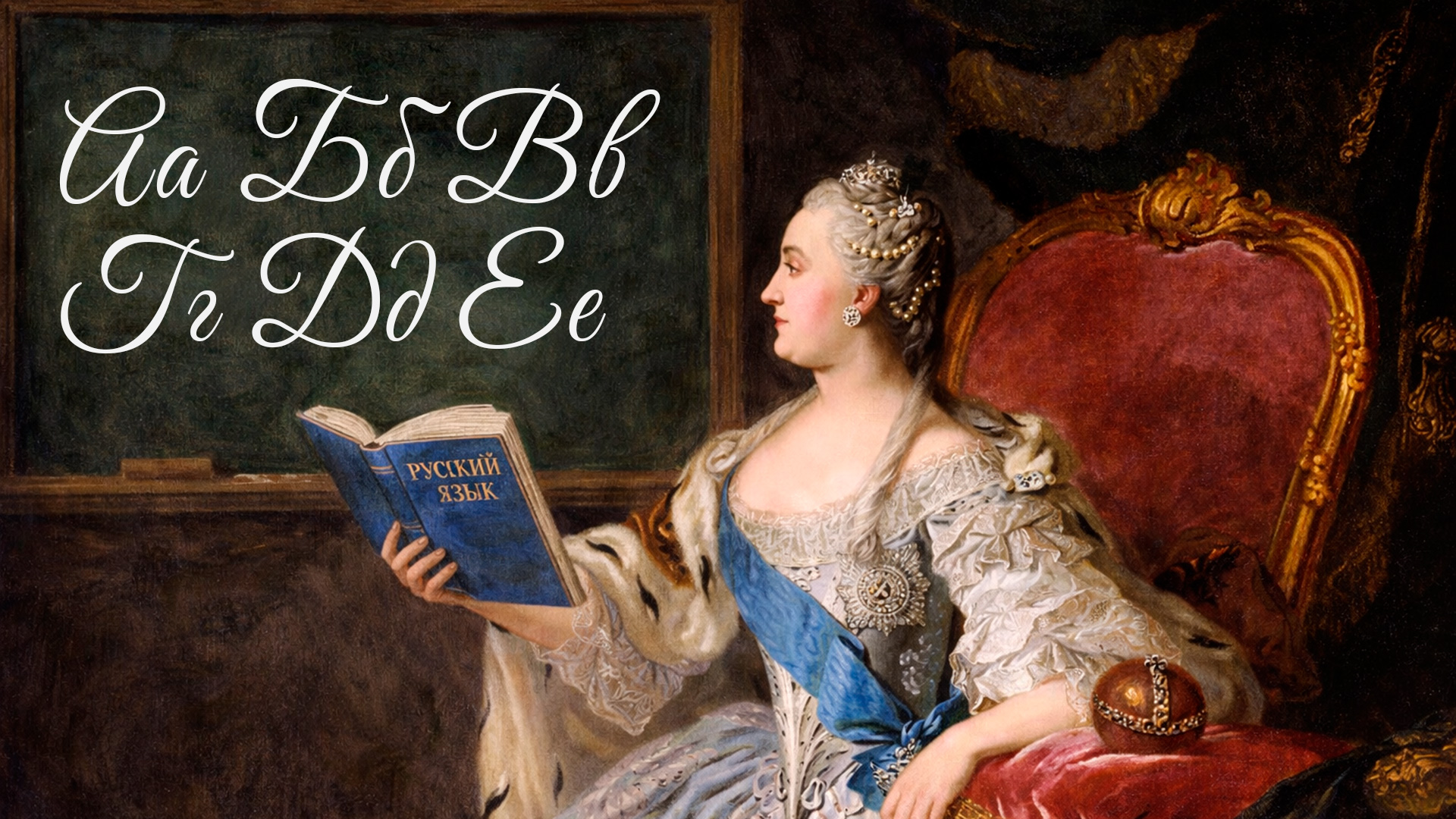
帝政ロシアの“金”を扱う人「ゾロタリ」とは誰のことか?

「暗闇のなか、“芳香”を放つ荷車の列が、ゆっくりと進んでいく。十数個の樽がそれぞれ、毛が抜けたぼろぼろの瘦せ馬に繋がれている。樽と荷馬車の間には、縄でできた座席があり、そこで『ゾロタリ』が居眠りをしている――モスクワでは、下水道作業員のことをそう呼んでいた。車列は、舗装された道路を、ときどき跳ね上がって、中身を石の上に撒き散らしつつ、区域全体にガタガタいう騒音を響かせる。そして真夜中過ぎには、そんな車列が、目抜き通りのトヴェルスカヤ通りの宮殿脇を、ノロノロと通り過ぎていく…。眠っている『ゾロタリ』がいる。把手を持ってカラーチを、もぐもぐ食べている者もいる(*カラーチは、把手のついた分銅のような形をした白パン。下の部分は、丸っこくて柔らかく、上の把手の部分は、パン生地でできてはいるが固い)」。
これは、ウラジーミル・ギリャロフスキーの著書『モスクワとモスクワっ子』(1934年)からの引用だが、いくつかの点で興味深い。
まず、「ゾロタリ」とは誰のことだったのかを教えてくれる。彼らは、汚水溜めから汚水を汲み出し、都市の公衆トイレ(例えば、兵舎や市場などの)を清掃していた。汚水を市外に運び出すか、専用の処分場に運ぶかしていた。
下水処理作業員がなぜ「ゾロタリ」というあだ名で呼ばれたのかについては、研究者によって意見が分かれている。もしかしたら、ユーモラスなあだ名だったのかもしれない(金細工師もまたゾロタリと呼ばれていた)。あるいは、排泄物が比喩的に「夜の金」と呼ばれ、肥料として使われていたからかも。
第二に、この車列は、「夜の芳香」と呼ばれていた。実際、汚水溜めは、柄杓で汲み上げられていたので、その臭いは長時間漂っていた。そのため、ゾロタリたちは、夜間に作業するよう命じられていた。しかし、注文が殺到すると、彼らは昼間に作業しなければならず、通行人は息苦しいほどの悪臭に耐えなければならなかった。
第三に、帝政ロシア時代のファストフードであるカラーチは、外出先で軽食が必要だが、手を洗う場所がない時のために発明された――こういう説が根強く残っている。カラーチは、細い「把手」の部分を持って食べ、そのまま捨てることができる。ゾロタリにとって、これは貴重な料理のアイデアだった。
19世紀、ゾロタリは高賃金で、しばしば他の多くの労働者よりも高かった。しかし、彼らの仕事は危険で大変な重労働だった。ゾロタリは、革製のエプロン、ブーツ、手袋を着用していたが、それでもなお、その仕事は、健康と生命を脅かす危険を伴っていた。寄生虫、細菌、感染症、硫化水素等のガスによる中毒などだ。












