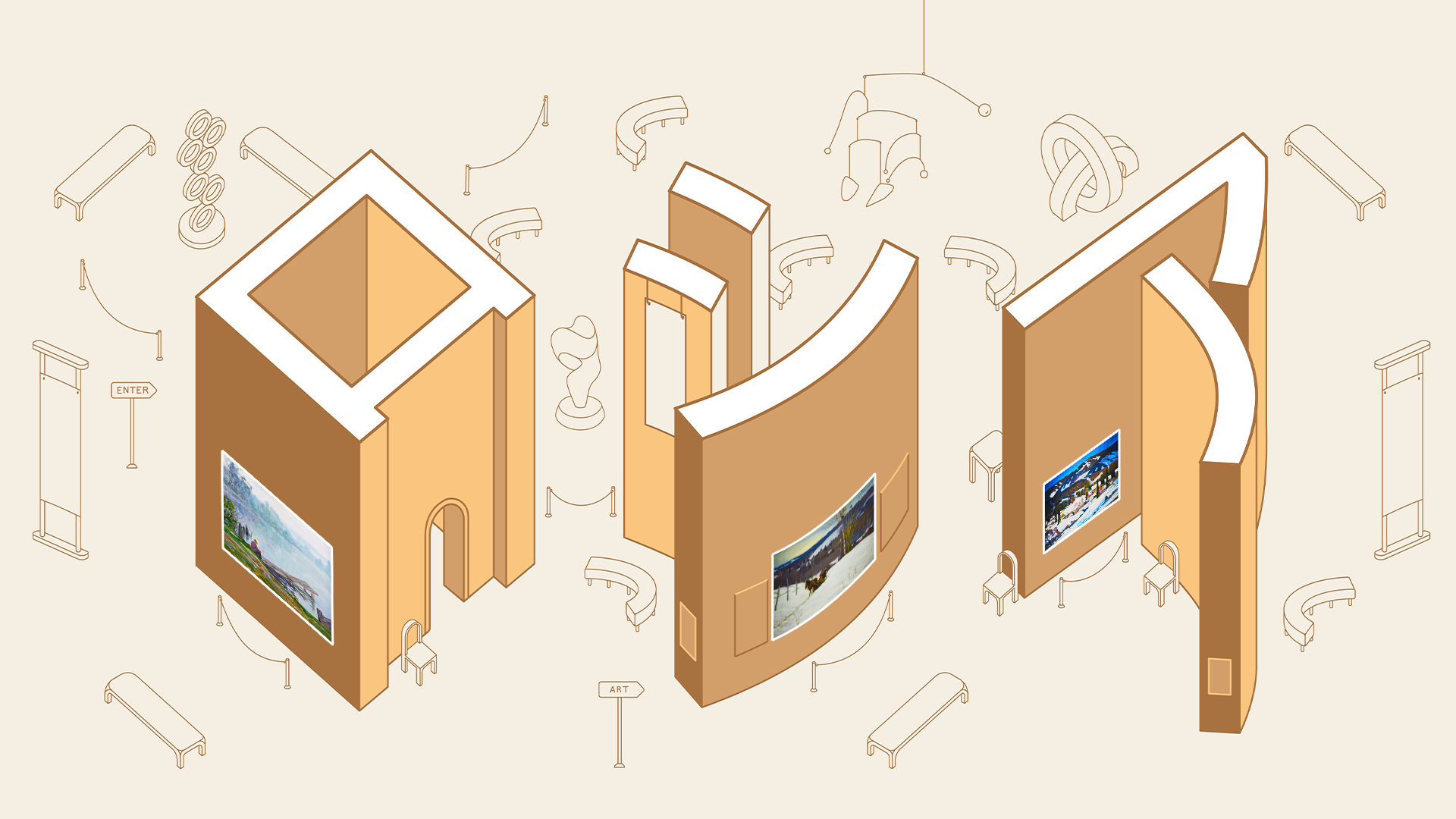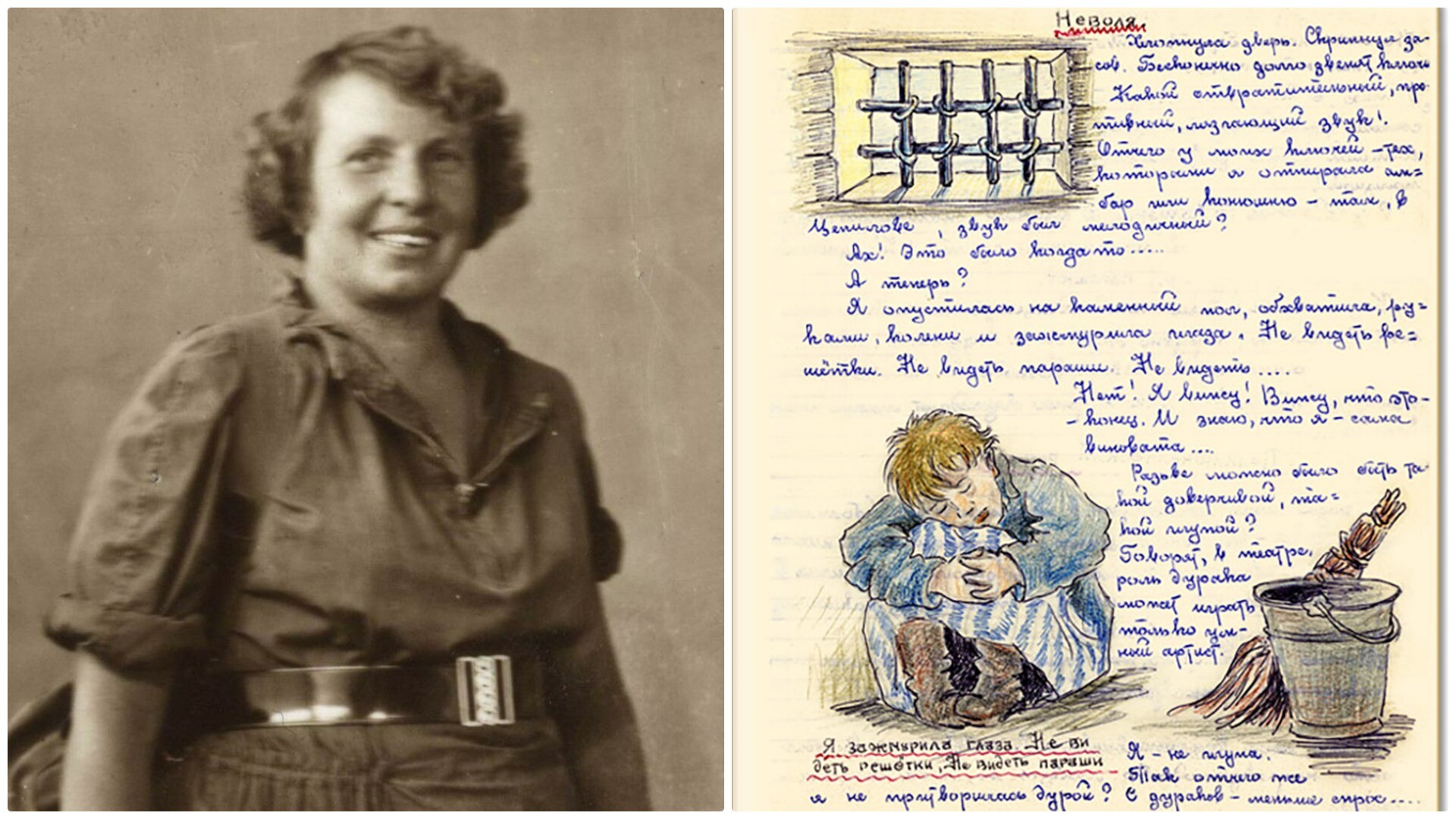ロシア人アーティストによって描き出されたダンス(写真特集)

「旋風」、フィリップ・マリャヴィン、1906年

印象派のマリャヴィンはダンスのエネルギーを形にした。マリャヴィンは、驚くほど派手なサラファンを着た一般の女性たちのダンスの様子をキャンバスいっぱいに描き、そのエネルギーはキャンバスからほとばしるほどである。
「噴水のそばで」、クジマ・ペトロフ=ヴォトキン、1906年

「革命の赤い馬」の作者であるペトロフ=ヴォトキンも、ダンスや民族的円舞の魔力に取り憑かれた一人であった。「噴水のそばで」は、ダンスをする少女たちが描かれた小さな作品。水っぽい絵の具、半透明なテクスチャー、軽快なタッチであるペトロフ=ヴォトキン独特のスタイルで仕上げられている。
「ホロヴォード」、ナタリヤ・ゴンチャロワ、1910年

ロシア・アヴァンギャルドを代表するアーティスト、ナタリヤ・ゴンチャロワは20世紀初頭のプリズムを通したロシアの国民文化を表現した。
「剣の中の舞」、ゲンリフ・セミラツキー、1881年

セミラツキーが考案した古代のテーマは、ローマへの旅行の雰囲気が漂っている。後期アカデミズムを感じさせる。19世紀末の「剣の中の舞」は批判されるものであり、とりわけ移動派たちからは、芸術において避けるべきものだとされた。しかしながら、この絵画を小さくした作品には、セミラツキーの作品の中でもっとも高価な値がつけられ、2011年のサザビーズオークションで、209万8,000ドルで落札された。
「古いバレエ」、コンスタンチン・ソモフ、1923年

革命前のロシアにおいて、バレエは帝国のすべての輝きと力強さを具現化し、ロシア貴族の主な財産の一つであった。ダンテの「神曲」を基に、ソモフが描いたバレエは、フランチェスコ・ダ・リミニの夫の弟に対する悲劇的な恋心を描いたものである。ニューヨークで高く評価されたこの作品は、1926年にオークションで落札され、その後100年以上にわたって失われたものと考えられていたが、2020年に再び、オークションに出品された。
「村のホロヴォード」、アレクセイ・サヴラーソフ、1873〜1874年

東スラヴの神聖なダンスであるホロヴォードは、結婚式、お見合い、雨乞い、収穫の始めと終わりなど、あらゆる機会に、村中の人々によって舞われた。ロシアの村を愛したサヴラーソフは、このテーマを描かずにはいられなかった。
「アルゼンチン・ポルカ」、カジミール・マレーヴィチ、1911年

テンポのある生き生きとしたポルカは当初は、貴族社会のみが踊った。その後、ポルカは、カドリールと同じように一般の人々のものになり、もっともロシア的なダンスになった。マレーヴィチは、「民間の」ポルカを、フォークロア芸術を模倣したもっとも民俗的なスタイルで描いた。
「ダンス」、ミハイル・ヴォロジン

ソ連共産党の献身的メンバーだったヴォロジンは、ロシアのダンスというお気に入りのテーマを、戦後数十年にわたってもっとも特徴的だった社会主義建設の場に移して描いた。
「バレリーナの控え室」、ジナイーダ・セレブリャニコワ、1923年

セレブリャニコワは、ダンスそのものではなく、バレエの楽屋をテーマにしたシリーズ作品を作り、バレリーナの控え室の華々しく、エキサイティングな雰囲気にフォーカスした。覗き見風、ドキュメンタリー風というのが得意な手法であった。
「カエルの王女さま」、ヴィクトル・ヴァスネツォフ、1918年

ヴィクトル・ヴァスネツォフは、ロシアでは、おとぎ話の挿絵のイラストレーターとして知られている。また逆に、ロシアのおとぎ話はヴァスネツォフが描いたものとして知られているともいえる。ヴァスネツォフは、王女さまがカエルから元の姿に戻り、お祝いでダンスをするところを描いた。
「村のダンス」、コンスタンチン・コロヴィン、1936年

コロヴィンは、1930年代、必要に迫られロシア国外に出た後で、記憶を辿って村の景色を描いた。ノスタルジックな感情が、コロヴィンにロシアの自然、トロイカ、祝日、そして村のダンスのシリーズ作品を描かせたのである。
「ダンス」、フョードル・スィチコフ、1911年

冬を送り、春を迎えるスラヴの祝日、マースレニツァのダンスは、ブリヌィを食べたり、ワラ人形を燃やすなどと同様、この祝日に欠かせないものである。
「商人の舞踏会」、イワン・クリコフ、1899年

19世紀の商人の舞踏会はきわめて高い人気を誇っていた。貴族しか参加できない有名な帝政ロシアの舞踏会と異なり、商人の舞踏会は誰でもが参加できた。商人は舞踏会に献品を持って参加し、またその他の人々は、高価なチケットを買って参加した。そのため、商人の舞踏会には、文化界の女神から裕福な役人や外国人までさまざまな人々が参加し、非常に楽しいものと考えられていた。