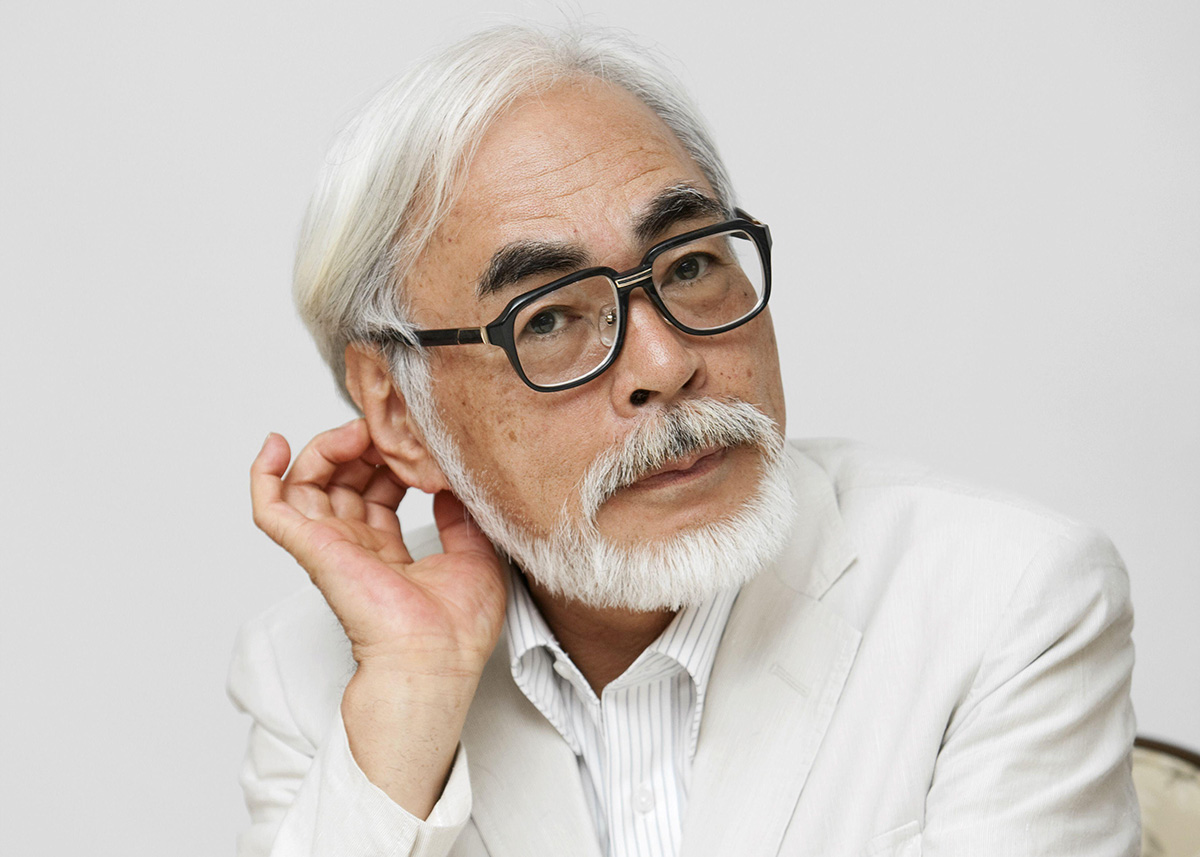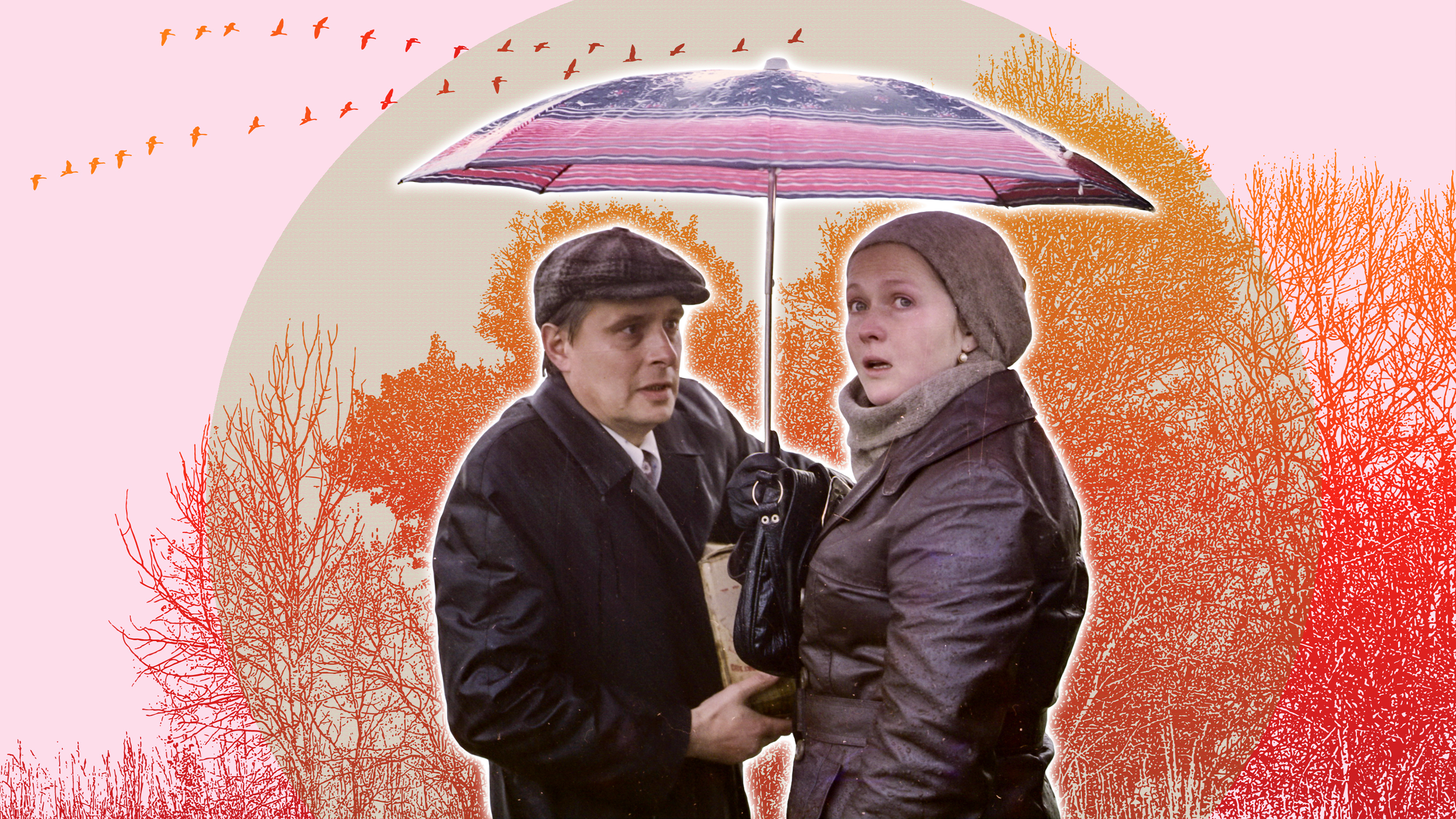Netflixドラマでウェンズデー・アダムスが演奏しているロシアの楽曲とは?

この楽曲の誕生にあたっては、それこそシェイクスピア劇なみの波乱があった。17年間を欧州で過ごしたセルゲイ・プロコフィエフは1930年代初め頃、ロシアへの帰国を考えるようになる。数回のソ連公演も行っていたが、その頃、レニングラード(現サンクトペテルブルク)のキーロフ劇場が『ロミオとジュリエット』の上演を計画していることを知る。
踊れないシェイクスピア劇

シェイクスピア劇用の作曲に意欲的になったプロコフィエフは、リブレットの作成に取り掛かる。この時、本筋はハッピーエンドに改変された。ラストで2人は生き残り、その愛も結実するのである。
当時としては大胆すぎる改変であり、このバレエは上演しないことに決定した。だが、リブレットだけが原因ではない。1936年にソ連のメディアで繰り広げられた、いわゆる形式主義批判キャンペーンも一因だった。
きっかけとなったのは、ソ連のもう1人の大作曲家ドミトリー・ショスタコーヴィチの作品だった。
「バレエ中の音楽は(中略)コルホーズともクバーニ地方とも、決定的に何の関係も無く(中略)ただうるさいだけで何も表現していない」
と、ショスタコーヴィチの『明るい小川』は酷評された。オペラ『ムツェンスク郡のマクベス夫人』については、
「左翼偏向的で、自然な人間的音楽のかわりに荒唐無稽」
と書かれた。
もとのシェイクスピアバージョンの結末に戻しても、キーロフ劇場は上演を拒否。続いてボリショイ劇場も「あまりに踊りにくい作品」であるとして同様に拒否した。プロコフィエフは上演を期待して、作曲したバレエ曲をオーケストラ用の組曲に編曲もした。このような経緯を経て1938年に初演がなされたが、初公演はソ連ではなく、チェコスロバキア。ブルノ劇場で初演を迎えた『ロメオとジュリエット』は案に相違して、じゅうぶんに音楽的かつ踊れる作品であった。ソ連の観客にお披露目されたのは、1940年である。
「悲しき物語」
「プロコフィエフのバレエ音楽ほど、この世に悲しき物語は無し」とは、『ロミオとジュリエット』を陰気に評したフレーズである。
初演の数週間前になって、キーロフ劇場オーケストラは興行の失敗を懸念して演奏を拒否した。ダンサーたちはリハーサル中、プロコフィエフの斬新な曲ではなく、耳慣れたメロディを口ずさみながら練習した。だが、杞憂だった。作品はスターリン賞を受賞し、1946年にはボリショイ劇場でも初演された。以降、このバレエは多くの国の劇場で上演され続けており、プロコフィエフの代表作の1つに数えられるまでになった。
中でも特に人気なのが、荘重ながら不穏な『騎士たちの踊り』である。この曲が、ロビー・ウィリアムズの『Party Like A Russian』で使われている。
そして最近では、ドラマシリーズ『ウェンズデー』にもこの曲が登場。ヒロインが無人の音楽室で演奏するシーンである。音楽室は闇に包まれ、ただ月の光だけがグランドピアノと空っぽの譜面台を照らす。
そして、ウェンズデーは弦が切れるまで演奏し続ける。
「それこそがプロコフィエフの影響力よ」
と、入って来た音楽教師が言う。まさしく、その通りだ。