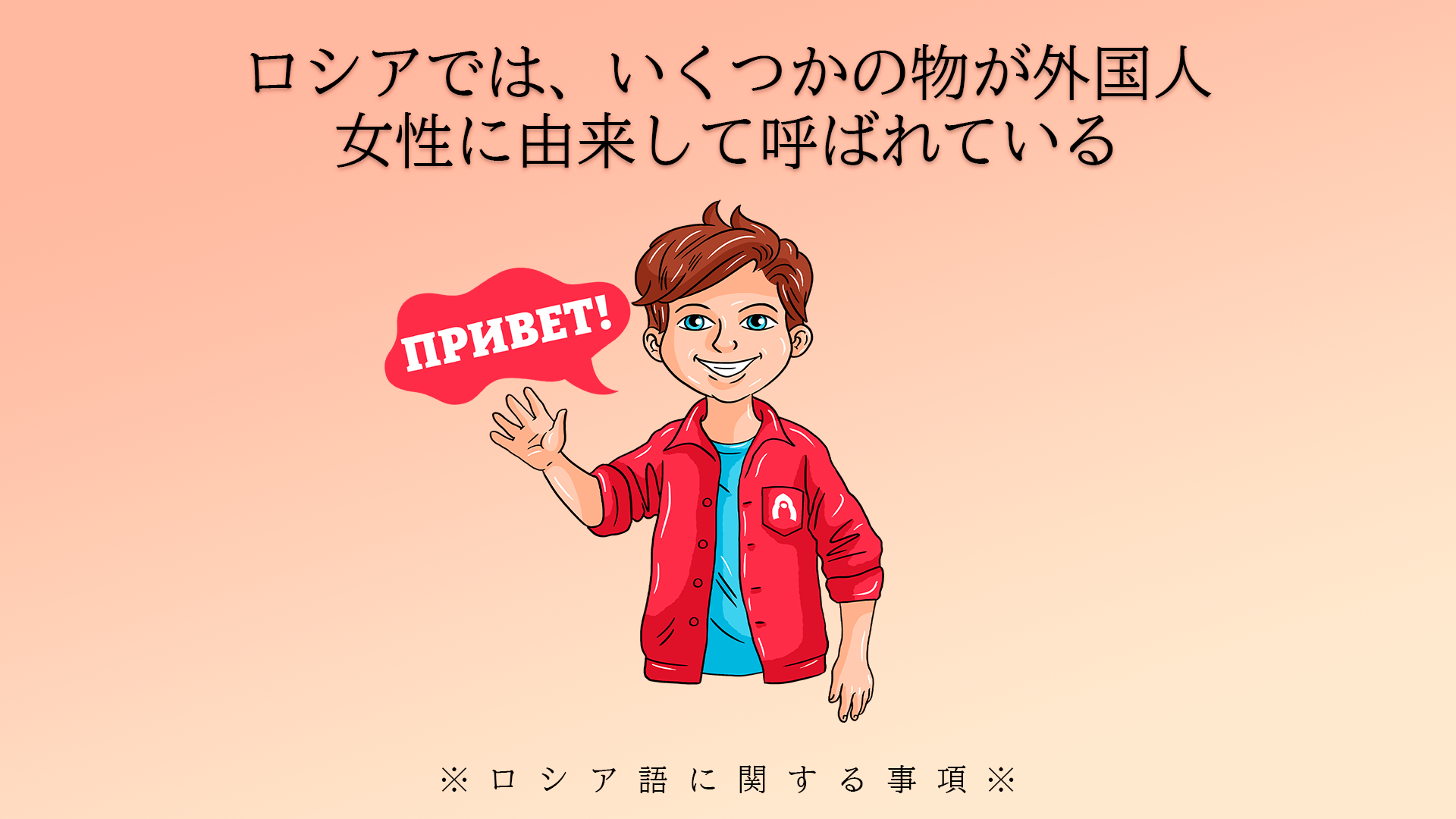「思考が木に沿って流れる」:この慣用句はどんな意味?

ちょっと分かりにくい慣用句のシリーズ。今回は、「思考が木に沿って流れる」。
「思考が木に沿ってあちこちに流れる」(растекаться мыслью по древу〈rastekat'sya mysl'yu po drevu〉)。ロシア語には、こんな表現がある。人口に膾炙しているが、この慣用句は、ロシア人さえも当惑させる。相手が話の本筋から逸れて、不必要な細部に迷い込んだことを仄めかしたいときに使われる… しかし、なぜ思考が「木に沿って流れる」のか、よく分からない。
このフレーズは、12世紀後半の、中世ロシアの名高い軍記物語『イーゴリ遠征物語』からの引用だ。その箇所の近くには、「灰色の狼」と「灰青色の鷲」が出てくるので、多くの研究者、そして後には、『イーゴリ遠征物語』を現代語に翻訳した人々は、こう推測した。これは、写字生の誤りであり、実は動物か鳥を含意しているのではないか、と。
例えば、「мысь」(mys')は、プスコフ方言でリスのことだ。もしそうだとすれば、理にかなっている。リスは、枝から枝へと飛び移る。そして、木に沿って「考え」(мысль〈mysl'〉)を広げる人は、一つの話題から別の話題へと飛び移る、というわけだ。
しかし、「白樺文書」(白樺の樹皮に記された文章)の解読を専門とする、著名な言語学者アンドレイ・ザリズニャクは、この作品には、「思考の木」(мыслену древу〈myslenu drevu〉という表現も含まれていることを指摘した。ということは、『イーゴリ遠征物語』の作者は、リスではなく、「思考が木の形のように広がっていくこと」、つまり現代のロシア語話者と同じく、「木を伝って流れる思考」を意味していた可能性があることになる。