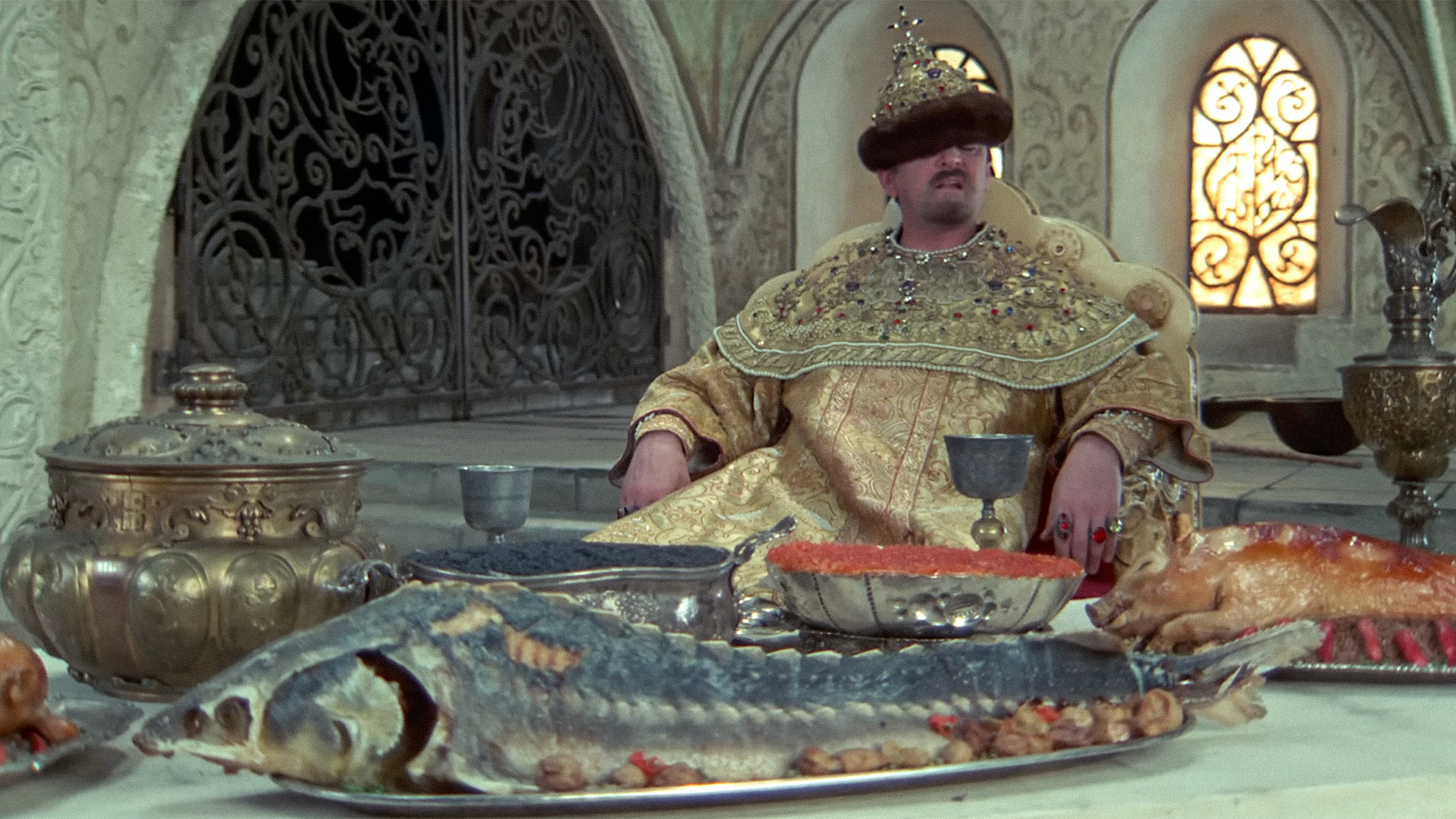モスクワで起きていたキノコ・ブーム

クレムリンの城壁の下では、19世紀からソビエト政権が樹立されるまで、有名なキノコ市場が毎年開かれていた。それは、48日間続く大斎「ヴェリーキー・ポスト」の初日に始まった。まるでモスクワ中の人々が、ここモスクワ河岸に集まったかのようだった。市場では、新鮮な野菜や塩漬けのそれなど、大斎期用の他の食材も売られていたが(*肉、牛乳、卵、動物性脂肪など、動物性由来の食材は禁じられていた)、主な食材は、あらゆる種類のキノコだ。人気の理由は簡単に説明できる。ボリュームたっぷりで、とても安いからだ。

「ここには、『魂を救う』ために必要なものなら何でもあった。塩漬けのチチタケ、ポルチーニ茸、マリネード漬けのナラタケが、巨大な樽や桶に入っていた。ザワークラウト、キュウリのピクルス、水に漬けたリンゴ、さやをむいたエンドウ豆等々が入った蓋なしの樽もあった。ここには何でもあった!大根、ジャガイモ、そしてあらゆる種類の野菜があった。テントの壁や、橇の上の長柄には、様々な品質の干したキノコが、長い糸状にまたは花輪状に吊るされていた。白と黄色の、あるいは安くて黒っぽいヤマイグチなどだ」。
作家ニコライ・テレショフは、市場についてこう語っている。

キノコは、あらゆるところから持ち込まれたが、主に「キノコ県」であるリャザン、オロネツ、コストロマから運ばれてきた。そこでは、キノコの調達が大規模に行われており、村全体がこの商いに従事していた。地元民は、キノコを採取した後、その場で調理し、マリネし、塩漬けにし、あるいは乾燥させた。そして大斎期の初めには、歯ごたえの良いキノコの入った桶や、干したキノコの「ビーズ」が、大量に売りに出された。

モスクワのキノコ市場は1週間しか開いていなかったが、人々は、大斎期の間ずっともつように、そこでキノコを買いだめしていた。キノコは、スープ、付け合わせ、前菜、ピロシキにしたり、サラダに加えたり、他の野菜と一緒に炒めたりした。

画家コンスタンチン・コローヴィンは、こう回想している。「村の馬をつないだ橇が一列に並んでいて、その上に大きな樽が積まれていた。羊皮の外套を着た男たちが叫んだ。『キノコ、キノコだよ!キャベツとキュウリの塩漬けもあるよ!』。キュウリ、キノコ、チチタケ、カラハツタケ、カラハツ、ベリャンカ(*チチタケ属)が入った巨大な樽…。ワシリーと私は、やっとのことで群衆をかき分けて進んだ」