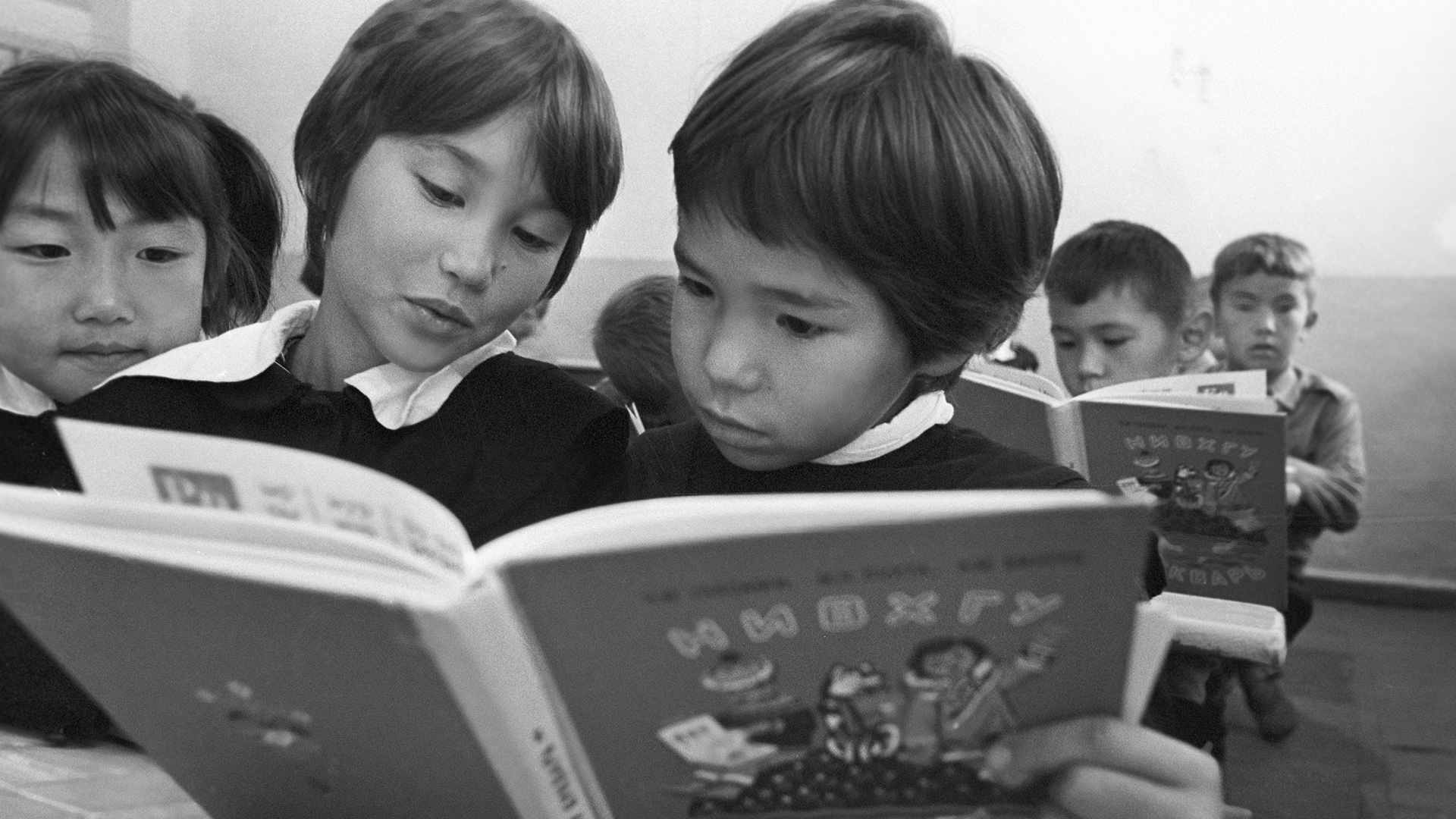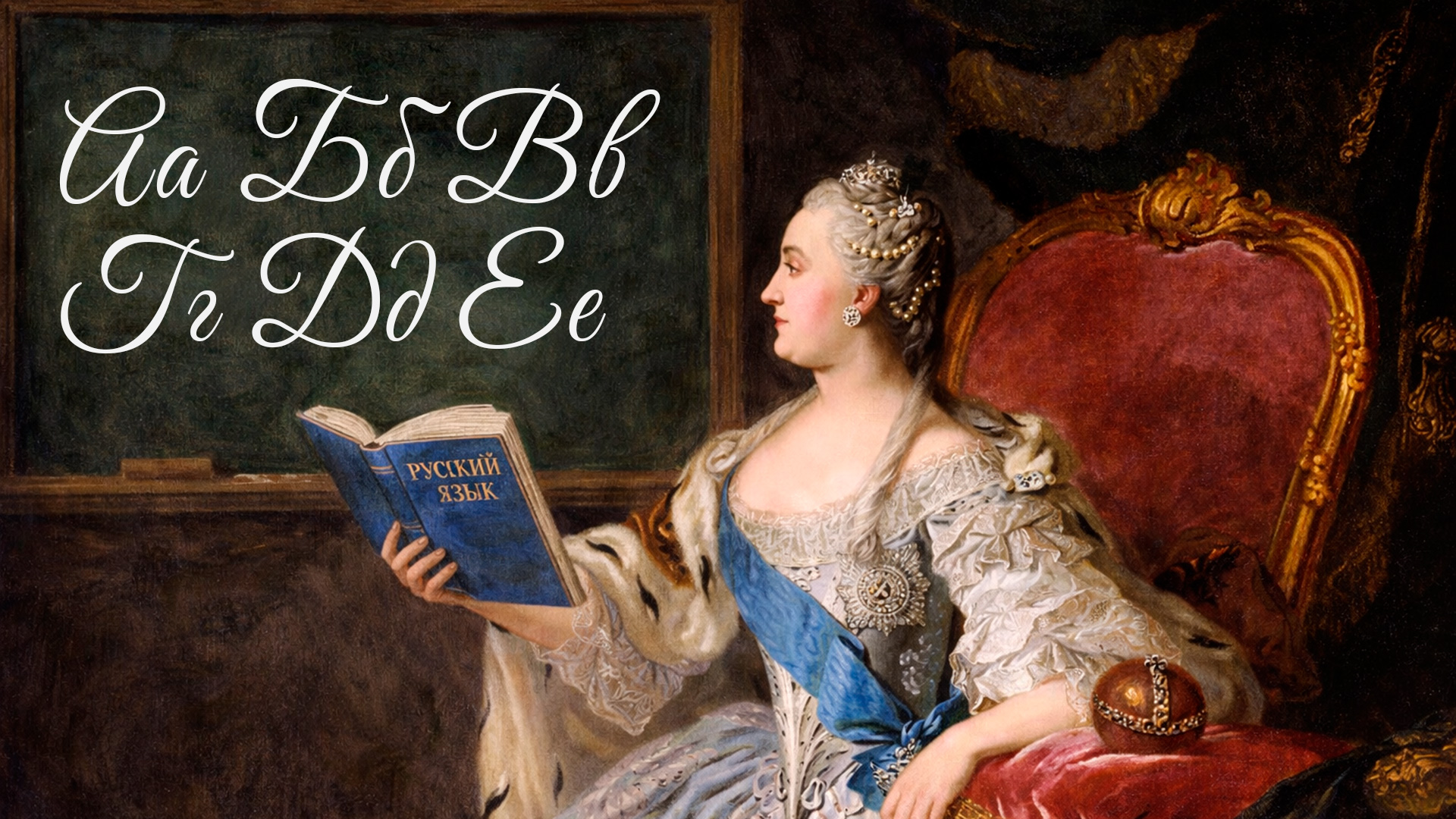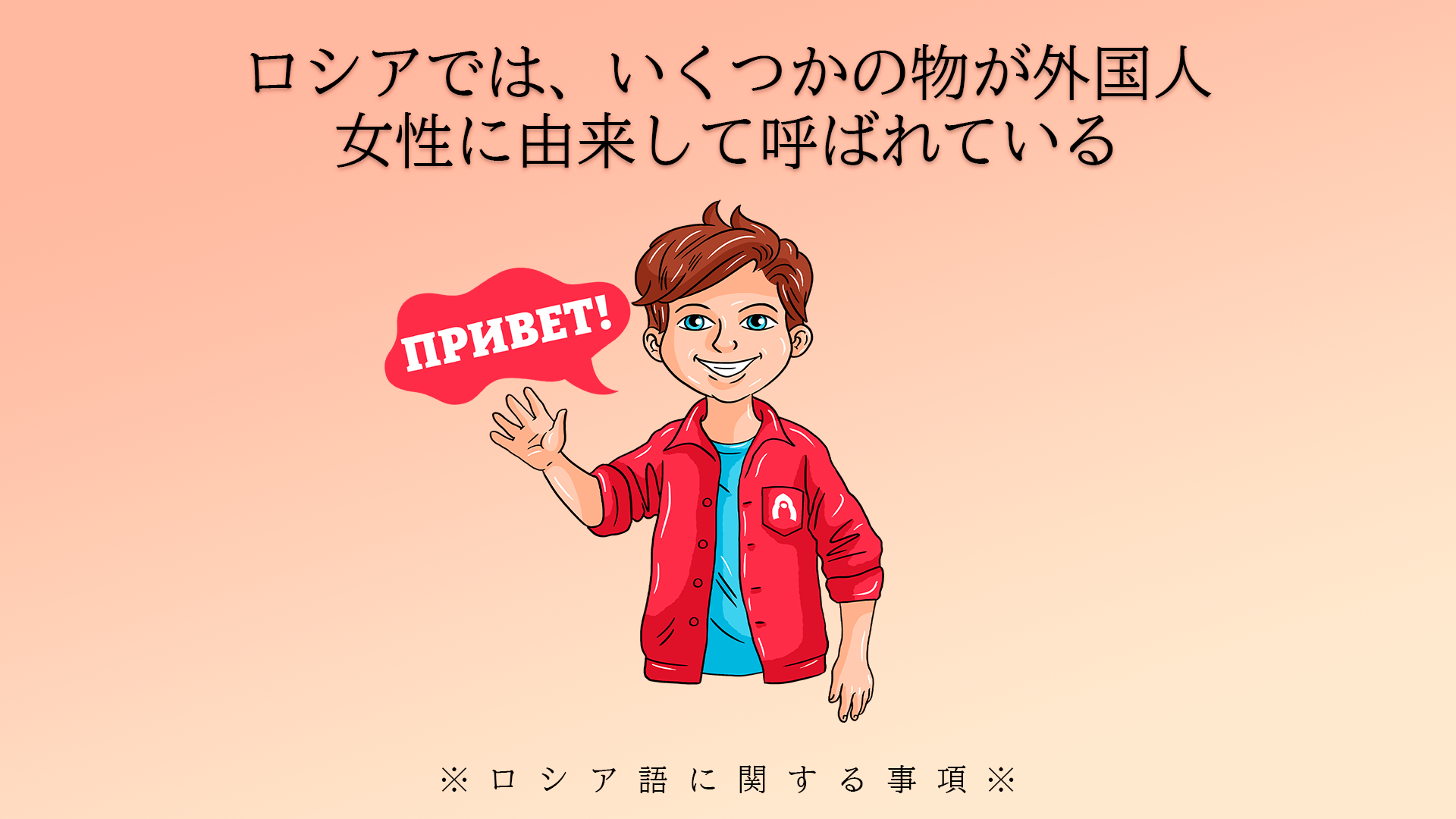「あいつは…で犬を食った」:この慣用句はどんな意味?

何かに秀でた人に出会ったら、その人について、「он на этом собаку съел」(彼はこの分野で犬を食った)と言われても驚かないように。これは、「この道に通じている」「お手のものだ」といった意味なのだ。
もちろん、その人は、誰も食べなかったし、そうする必要もなかった。この表現はもともと、「犬を食ったが、尻尾で喉が詰まった」という諺から派生したものだ。どんなに難しい課題をこなせる人でも、些細なミスを犯して失敗することがある、ということを表している。「猿も木から落ちる」、 「弘法も筆の誤り」といったところだ。
19世紀には、この諺の前半部分が普及し、日常会話や文学で用いられるようになった。例えば、アントン・チェーホフの中編小説の主人公は、知人についてこう言う。
「…彼の素性は誰も知らないが、驚くほど頭が良く、こと哲学となると、犬を食った(→精通していた)」(『ともしび』、1888年)